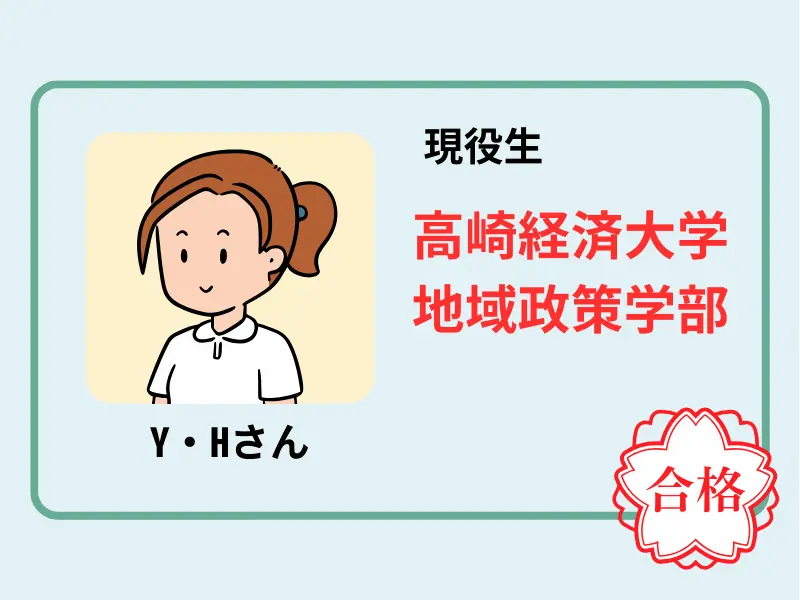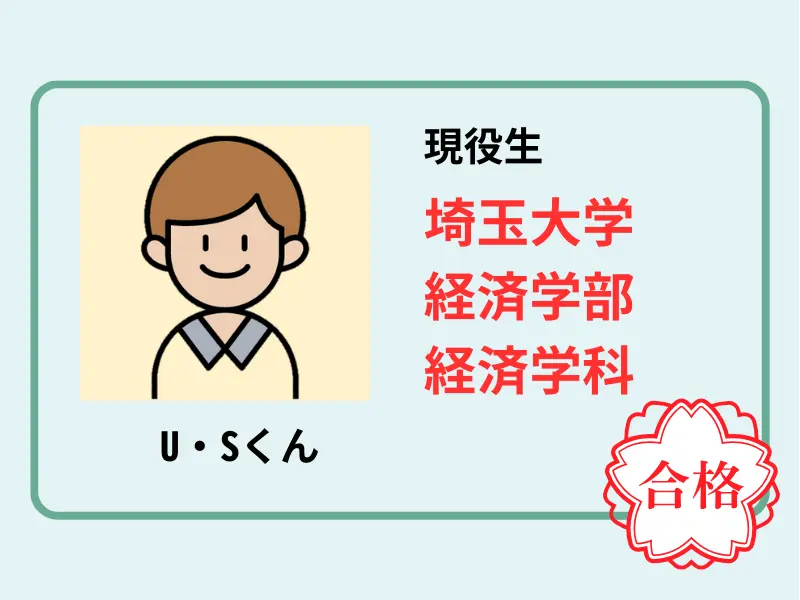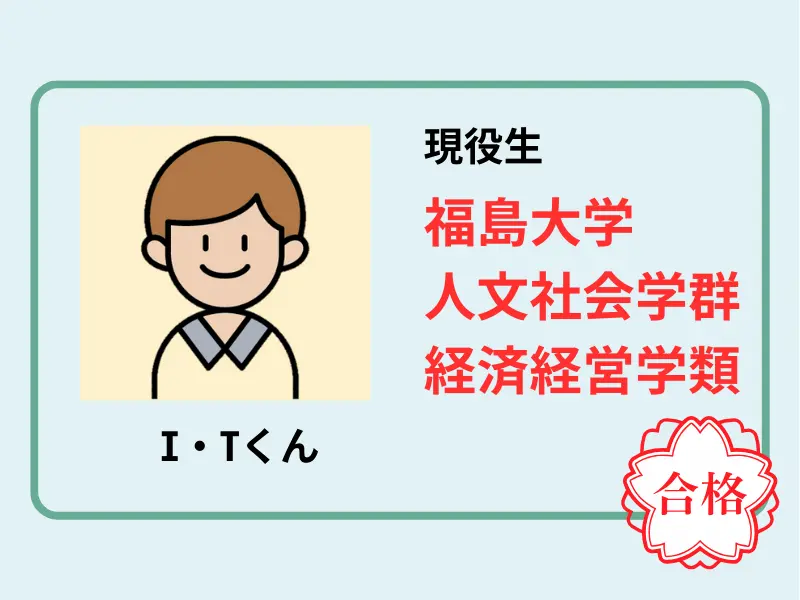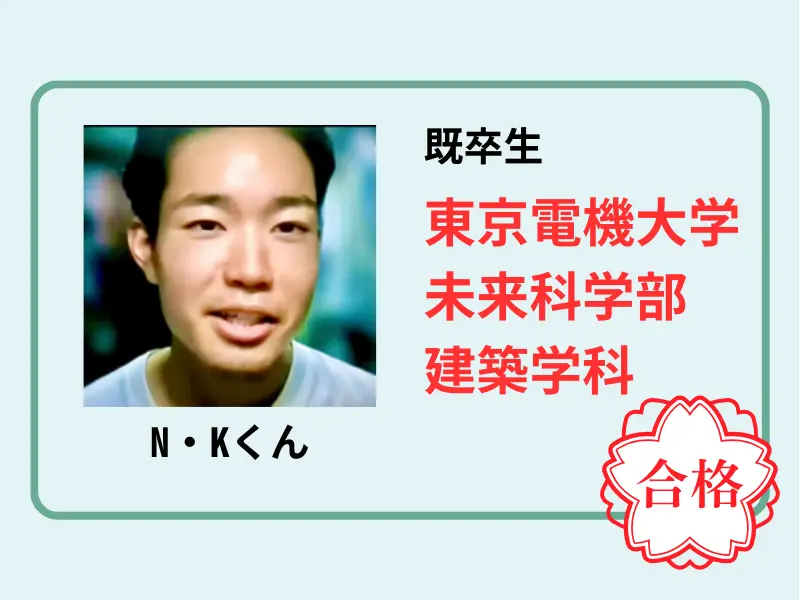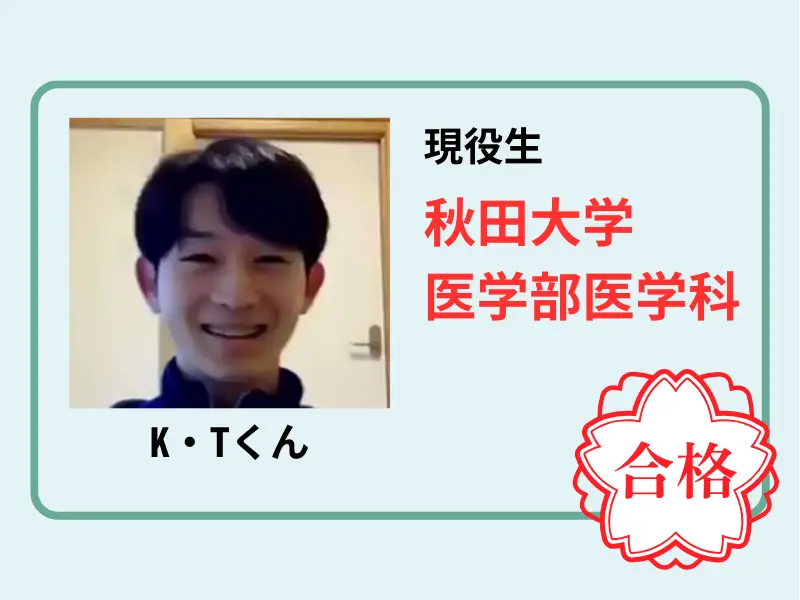横浜国立大学 理工学部 数物・電子情報系学科 物理工学EP 合格体験記
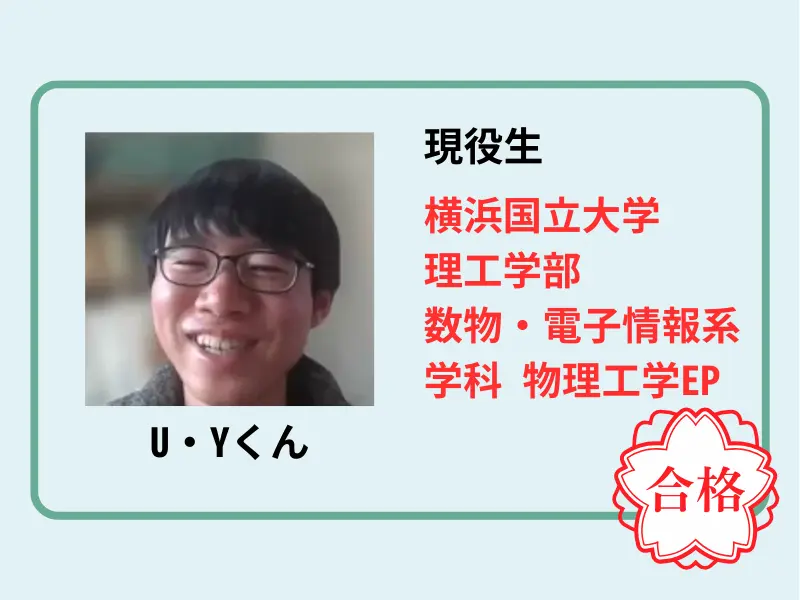
SoRa入塾前の状況
私が入塾したのは高2の夏です。それまでの私は「好きな科目を好きなときに好きなだけやる」という漫然とした勉強をしていました。事実高1のときは学校の定期試験や模試で戦えたので、「この調子でいけば難関大合格を目指せるのではないか」と思っていました。
ところが高2の2月に学校で受けた模試では、成績を維持するどころか総合点の校内順位が下がりました。
自分では手抜きをしたつもりはなかったので、「このままでは理由もわからないまま同級生にリードを奪われ、原因の自覚ができないまま大学合格への道から遠ざかってしまうのだろうか」という不安を感じ始めました。特に数学と物理に関してです。
そのような中で SoRaの先生方に出会いました。「映像授業や集団授業を受け身で受講しても課題が浮き彫りにならず、伸びなさそう。それよりも正しい学び方を身につけ、効率良く自学ができるようになる方が賢明だ」と考えたのです。
3月の合格発表の直前までずっと、先生方は本当にたくさんのアドバイス、手厚いサポートをしてくださりました。
SoRaに入塾してからの変化
多くの発見がありました。 何よりもまず、高2まで私が1人でやってきたことと受験勉強で本当にやらなければいけないこととは、方向性にずれがあったということです。
私は「勉強することが好きな方だ」と思っていました。知識が増えて好奇心が満たされると幸せだからです。しかしそれは大学入試攻略というゲームにおいては、あくまでもコレクションの要素を楽しんでいるプレイヤーに該当します。
受験生として本当にやりこまなければいけないのは、むしろ対戦の方でした。仲間を増やしたりレアなアイテムを拾ったりするだけでは不十分で、技を自在に放てるようにならないと当然勝負には勝てません。
高3になって初めてそのことに気がつきました。そこから今まで意識的にやってこなかった、一通り学んだ基礎問題と入試の典型問題が本当に自力で何も頼らずにすらすらと解けるようになっているのかを確認する作業をするようになりました。
ときどき興味本位で難しめの問題に出会い、答えを見て時間をかけてなんとか理解をすることがあっても、実際の試験でその経験を使いこなすことは難しかったです。それよりも、自分が胸を張って解ける問題を体系化しておくことが自信に直結しました。
私は高校入試のときからずっと、易しめの問題もかなりの難問もいずれは全ての問題を解けるようにならなければいけないのだと勝手に思っていました。しかし現実的にそれは不可能で、学力の似たライバルが得点する問題を自分も間違えずに解ききることの方が大切だったのです。
それで十分に例年の合格者平均点を目指すことが可能です。試験当日は、「完答できなくても今まで学んだことをやれるところまで自力で組み合わせればそれでいい」という気持ちでいました。
先生方と話し合って計画を立てることで戦略が明確になり、結局は地道な基本事項の復習を怠らないことが合否を分けるのだということに気づいたからです。
また、私は疲れやすい体質で、夏休みは1日8時間ほどというまわりの受験生の平均よりも短い時間しか集中できていませんでしたが、冬休みは徐々に就寝時間を遅らせ、最終的に入試直前期に10時間以上の勉強を続けられるようになりました。
無意識に自分の限界を決めている節があったのだと思います。受験勉強は、自分の本気の状態を知る大事な機会になると感じました。
他にも、私には難問に粘り強く立ち向かい切れず、すぐに解答解説を求めるせっかちな部分があります。先生方に指摘されるまで、自覚を持っていませんでした。客観的に分析することで自分の特性と向き合うようになり、思わぬところで精神的にも成長できたと思っています。
受験勉強で苦労したこと・それをどう乗り換えたか
私は入試数学の思考問題が未だに苦手です。大問が1つあって、(1)(2)までは類題を解いたことがあるから簡単に答案を書ける、しかし(3)(4)で急に初めて目にするようなことを問われるから一切考えが進まず、何も書けなくなる。というような事象が多発します。
先生方は、解くときの姿勢を私に何度も強調して教えてくださりました。
まずこういうときは、「必要な知識は自分の頭の中に全て入っているのだから、やるべきことはそれを取り出して組み合わせるだけだ」という心持ちで腰を据えることです。初めての話に見えても、結局は今までの基本事項を積み重ねているだけだったという見かけ倒しの数学の問題は本当に多かったです。
人の脳の性質上、未知のものだと思い込んだ瞬間ストレスで逃げ出したくなるのかもしれません。しかしここで堪えて立ち向かう力のある人を、大学はきっと求めています。
こんなとき、参考書のような模範解答をすらすら閃くことは私のような常人にはできません。もっと人間らしく、無理のない方法を教わりました。たとえば、知っている公式をとりあえずそのまま書き出してみるということです。
何も意図はないけれど数Ⅲの問題であるから極限の公式を書いてみた。なんだか問題の計算式もそれと似たような形をしているから公式の形に近づける式変形を試みた。するとうまくいってしまった。ということが実際にありました。
自分でヒントになりそうな事項を紙に書き出すだけで、何もできずに終わっていたかもしれない問題に手をつけられるようになったのです。
他にも、意味が無さそうであっても不等式を XY 平面上のグラフに対応させて考えることで重大な位置関係の情報が手に入ったり、とりあえず漸化式の第 5 項目までを直接の計算で求めたり確率の問題を自分でスケールの小さい状況に置き換えて考えたりすることで、規則性がわかって思考が進んだりするという経験をしました。
何の意識もなしに問題をたくさん解いているだけでは数学は得意にならず、自分がかき集めた知識、ヒントを最大限に用いることで問題を解いてやろうという意志を持つことが必要だと学びました。
図を丁寧に書くことはミスの防止にもつながります。どの科目でも、なぜこのように問題を解くとうまくいきそうだと思ったのかという問いかけを常に自分にすることで、論理的に知識を活用する練習になり、実力をつけられるようになっていったと思います。
【LINE友だち追加特典】
—❶ 数学やるべき参考書MAP
現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、
今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。
・ 学力段階ごとにおすすめの参考書
・ どんなタイプの人に向いているか
・ 使うときに気をつけるポイント
などを具体的に解説しています。
—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム
公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。
このコラムでは、
実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、
高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。
・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方
・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法
・ 部活動と勉強を両立する考え方
・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法
など、
少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。
ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。