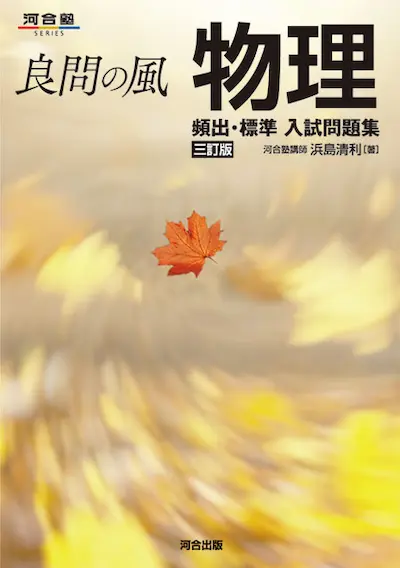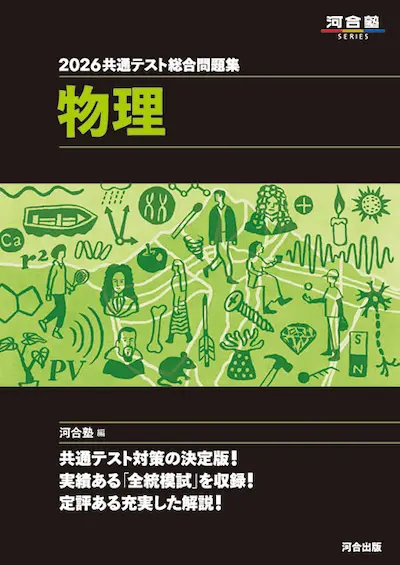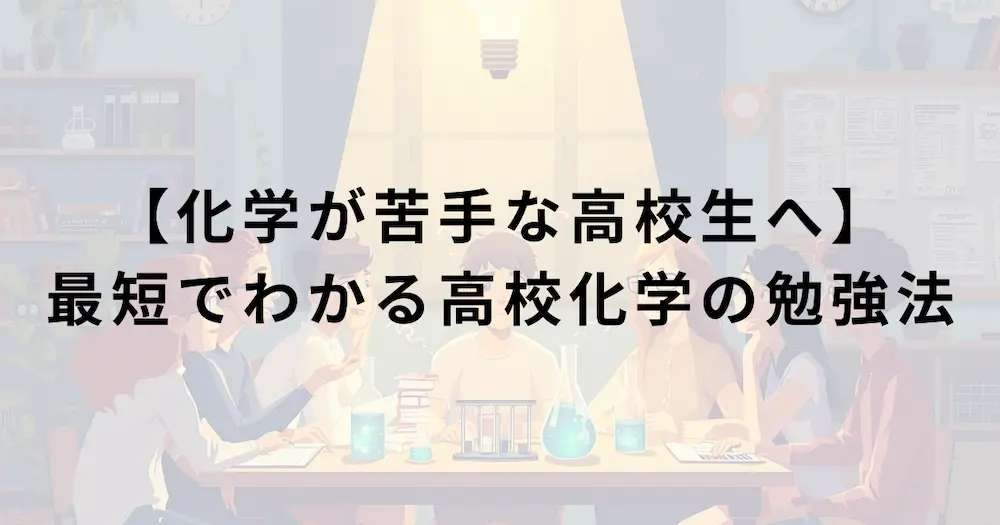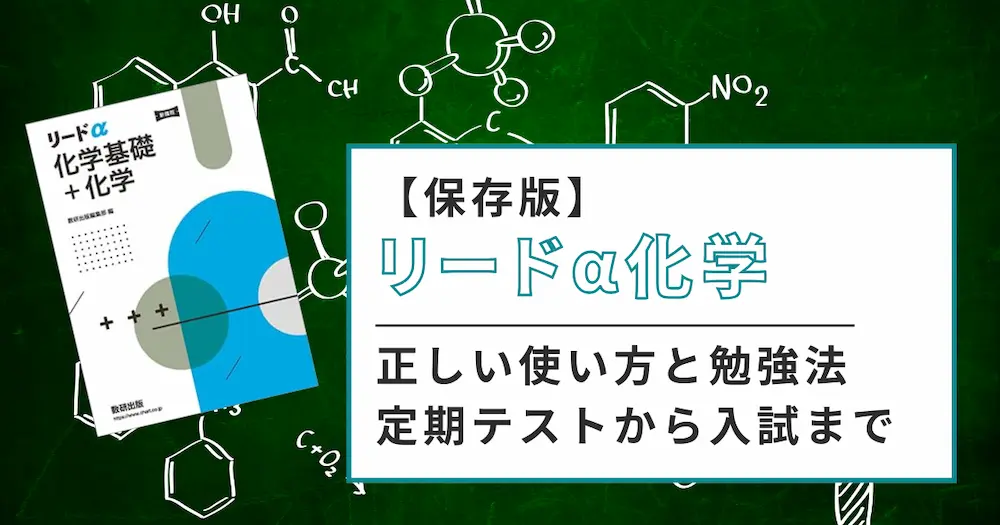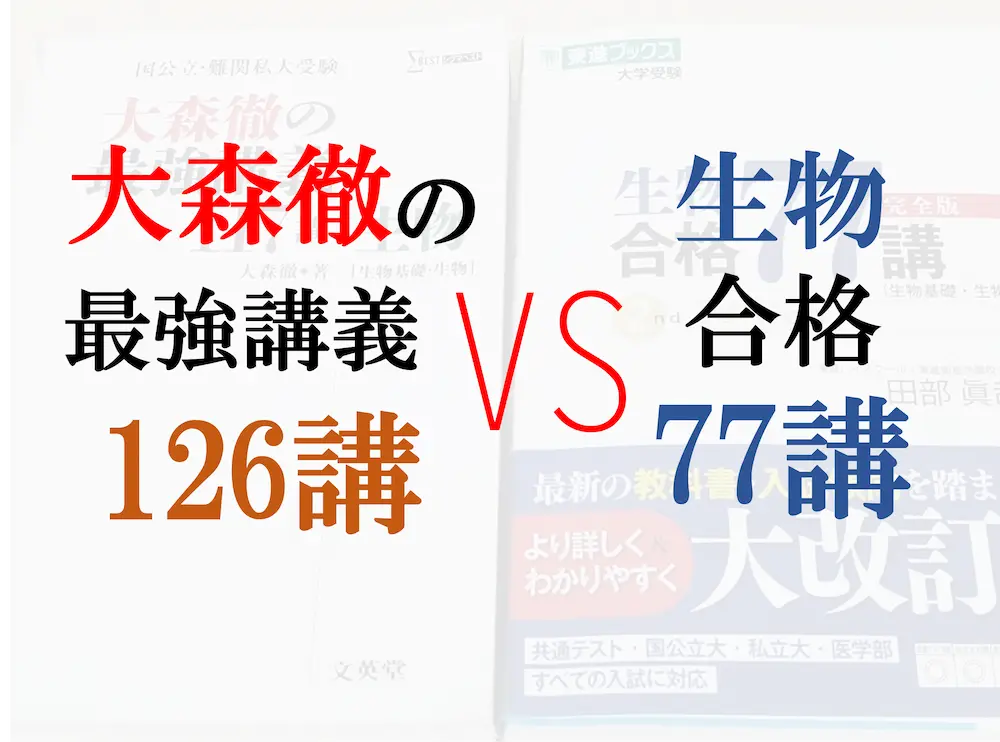【徹底解説】物理のエッセンスの使い方・レベル・難易度|最適な勉強法
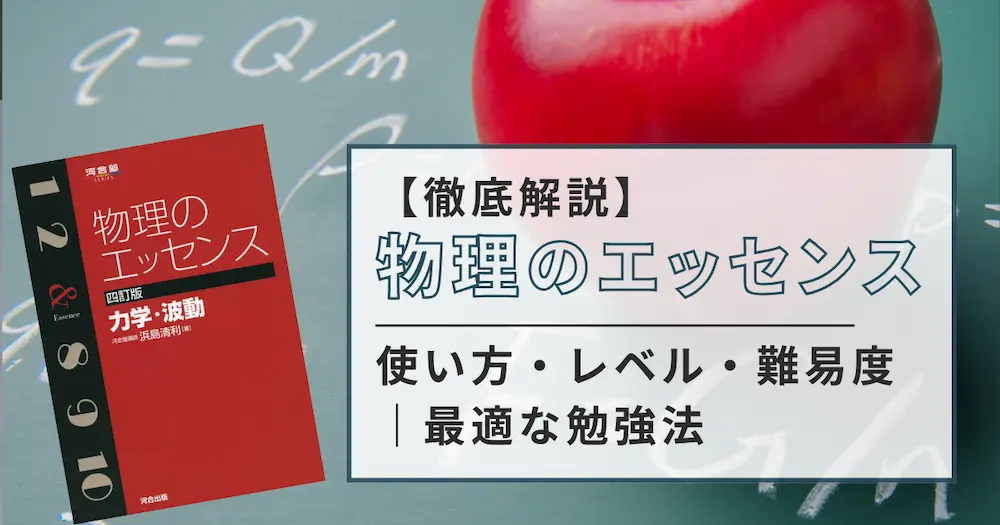
こんにちは、理系のための大学受験塾SoRaの百瀬です。今回は、大学受験の物理において王道の参考書「物理のエッセンスのレベル・難易度・使い方」について、理系専門塾の塾長が徹底的に分析し、解説しています。
物理のエッセンスは受験物理の定番参考書ですが、使い方を誤るとまったく学力が伸びない上に、物理を嫌いになってしまいます。本記事では、物理のエッセンスのレベルや使い方、そして効果的な勉強のコツを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
【この記事を読むべき人】
- 物理のエッセンスの評判や使い方を知りたい人
- 物理のエッセンスで物理の苦手を克服したい人
- 物理のエッセンスを使っているが伸び悩んでいる人
- 物理のエッセンスをいつから・いつまでにやればいいか知りたい人
- 大学受験や学校の定期テストで物理の点数を上げたい人
【自己紹介】
百瀬 浩市
理系のための大学受験塾SoRa/個別進学塾TaNeの代表。
自らも生徒指導にあたり数学・物理・化学・英語と幅広い科目を指導。理系の道に進みたいけど、数学が苦手な子の助けになれるよう日々邁進中。
物理のエッセンスとは?
物理のエッセンスとは、河合出版が出版している物理の定番参考書です。著者は浜島清利先生で、受験界では長く使われている名著となっています。「力学・波動」編(169頁+別冊解答)と「熱・電磁気・原子」編(166頁+別冊解答)の2つに分かれています。
そして各編、物理の考え方を詳しく解説した丁寧な説明と、入試レベルの基礎〜標準問題を扱った例題と演習問題が収録されています。つまり「物理のエッセンス」は、基礎から標準レベルの典型問題を押さえつつ、大学入試に必要な思考力を養える参考書だと言えます。
物理のエッセンスの特徴・レベル・難易度を解説
内部構成は各分野で次のようになっています。
- 導入の説明
- ポイントの整理
- 解法の解説
- 例題と解説
- 演習問題
「物理のエッセンス 浜島清利著 五訂版」を参照し、各分野の問題数をまとめると以下のようになっています。
| 分野 | 各分野の収録問題数 | |
|---|---|---|
| 物理のエッセンス【力学・波動】 | 力学 | 116問 |
| 波動 | 70問(うち力学的波動は52問) | |
| 物理のエッセンス【熱・電磁気・原子】 | 熱力学 | 33問 |
| 電磁気 | 98問(うち磁気分野は42問) | |
| 原子 | 40問 |
本書の冒頭には「物理は考え方の流れが大切だ」と書かれていますが、それに準じて直感的な理解を促進するような解説が丁寧に書かれています。また各例題に対して練習問題が3〜5問程度準備されており、難しい問題の解き方も習得することができるようになります。
物理のエッセンスの中には、
- 「Miss」
- 「ちょっと一言」
- 「High」
- 「Q&A」
- 「知っておくとトク」
という欄があり、学習中の疑問や注意点が記されています。
多くの学習者が間違えるポイントや注意事項が記載されており、続く練習問題で演習を積みながら意識を高めることができる構成になっています。また物理が得意な人向けのメッセージも記載されており、高校物理に範囲にとらわれない本質的な理解を促してくれる構成です。
物理のエッセンスの難易度およびレベルは「基礎〜標準レベル」です。正しく使い進めれば、苦手の克服から共通テスト8割以上を目指せる力が身につきます。学校の定期テストはもちろん、大学受験の2次試験で物理を使わない場合には、物理のエッセンスだけで十分に入試対策を行うことができると言えます。
また難関私立大学や難関国公立大学を目指している人は、入試レベルの演習に入る前に定石を身につけることができます。その後の問題演習を積むための基盤を作ることができるでしょう。
物理のエッセンスはゴミなのか?実際のリアルな感想と評判
ただし、物理のエッセンスを用いて勉強する際には注意が必要です。実際に、物理のエッセンスは、大学受験参考書の定番となっている一方で、賛否が分かれているのも事実です。インターネット上では「物理のエッセンス ゴミ」「練習問題が難しい」「物理ができるようにならない」などの声も確認されます。
確かにその通りで、私自身これまで多くの受験生を見てきましたが、やり方を間違えるとほぼ確実に失敗します。 実際、私も受験生のときに物理のエッセンスをやりましたが、あまり手応えを得られませんでした。
物理のエッセンスをやるうえでの注意点は後述しますが、よくある失敗パターンは、
- 「解説を読んで分かった気になり、演習を繰り返さない」
- 「例題だけを眺めてノートにまとめて終わり」
- 「練習問題が解けずにそのまま放置」
などです。こうした取り組み方は、決して「良い学習法」とは言えないでしょう。そして公式や解法の流れが定着しにくいため、試験本番で一問も解けない、という悲惨な結果になってしまいます。
つまり少し残酷なことを言うと、物理のエッセンスは正しい使い方をすれば非常に強力ですが、誤ったやり方をすると一生物理ができないまま終わってしまう危険があるということです。
とはいえ、始める時期や目指す志望校、自分の数学力などをしっかりと把握し、適切な使い方を知った上で丁寧に学習を進めていけば問題ありません。ここからは物理のエッセンスをいつから始めればいいのか、またどのレベルまで到達できるのかについて具体的に紹介していきます。
物理のエッセンスの対象者と到達レベル
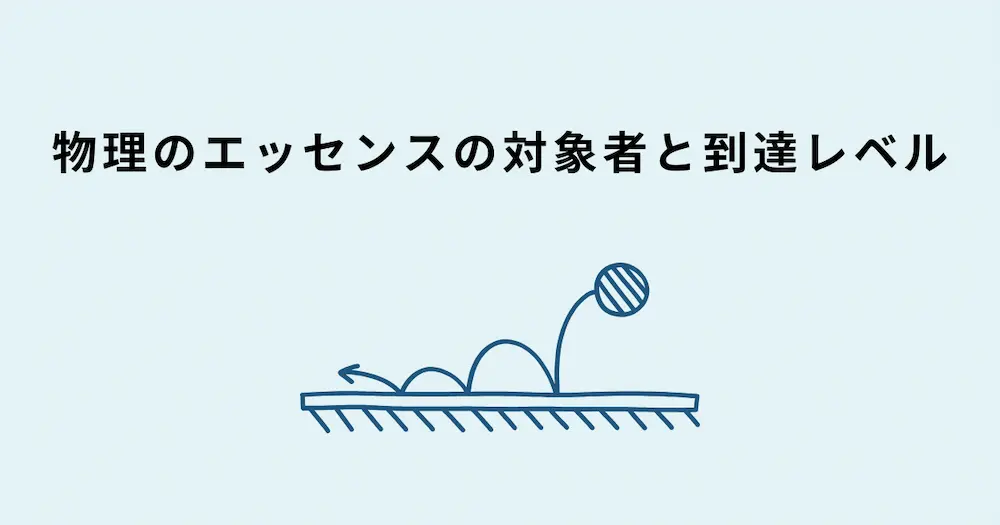
物理のエッセンスはいつから使う?
物理のエッセンスをいつから使うべきかは、学習状況や数学の理解度によって大きく変わります。やはり物理とはいえ、「本質」の理解のためにはどうしても数学の知識が必要になります。そのため、学年ごとに注意すべきことが異なります。
高1から始める場合には、理系を志望していて早めに基礎を固めたい人には有効です。ただし、高校1年生の段階では説明を理解するための数学の計算力が十分でないことも多く、その状態で取り組むと「公式の暗記」や「例題の丸写し」に終わってしまう危険があります。
数学ⅠAⅡBの内容が定着している生徒であれば、エッセンスを通じて物理的な思考法を身につける良いトレーニングになります。
高2から始める場合がもっともおすすめです。学校の進度に合わせて並行して予習復習が進められるため、習った分野を、物理のエッセンスで整理し、標準問題に触れて定着を確認するというサイクルが作れます。この段階で物理のエッセンスをしっかり周回しておくと、高3に入ってからの「良問の風」や「名問の森」への移行がスムーズになり、入試本番で戦えるだけの演習量を確保できます。
高3から始める場合は、5月までに始めることがタイムリミットです。
夏以降に取り組むとなると時間的に厳しくなってしまいます。物理のエッセンスは、説明参考書にしては比較的問題数が多く、すべてを網羅するのは現実的ではありません。
そのため例題を中心に効率良く進め、苦手分野や頻出分野は練習問題まで解くというのが現実的な方法になります。共通テスト対策や基礎固めにはまだ十分間に合いますが、難関大を目指す場合には同時並行で入試レベルの演習に進まなければ間に合わない可能性が高いです。
結論として、最も効果的な開始時期は高2からです。高1は数学力が十分なら挑戦してもよいですが、多くの生徒は高2からが適切です。そして、高3は「優先順位をつけた取捨選択」が必要になってくることを注意しましょう。
ここで大切なのは、自分が本当に正しい勉強法で進められているかを客観的に判断することです。どんなに注意をしても、自己流で進めてしまえば「解説を読んで満足してしまう」「復習が形だけになる」といった誤りに気づけないまま数か月を無駄にしてしまうことが生じます。塾や指導者に相談することで、自分の取り組みが正しい方向に向かっているかを確認でき、効率よく成績を伸ばしていくことができます。
物理のエッセンスだけでどの大学レベルまで対応できる?
物理のエッセンスは「基礎〜標準レベル」に位置づけられる参考書です。そのため、共通テストで8割を目指す受験生や、国公立中堅大学・MARCH・関関同立といった標準的な難易度の私立大には十分対応できます。
実際、物理のエッセンスをしっかりと習得していれば、基礎〜標準問題で取りこぼすことがほとんどなくなります。特に共通テストでは、出題の意図を読み取ることができるようになり、安定して得点することができるようになります。
一方で、東大・京大をはじめとする旧帝国大学や医学部などの難関大学では、物理のエッセンスだけではどうしても不足します。理由は明確で、入試本番では「典型的な解法を少しひねった問題」や「複数分野をまたぐ融合問題」が頻出するため、エッセンス内の分野ごとの練習問題だけでは対応力を養えません。内容の本質的な理解や解法の基礎力を物理のエッセンスで固めたうえで、必ず「名問の森」や過去問を中心に発展的な問題集に取り組む必要があります。
併用する参考書・問題集は?
物理のエッセンスは、基礎〜標準問題の「定石の確認」には最適な参考書です。内容そのものは非常に優れていますが、実際には多くの受験生が「正しく使えない」という理由で挫折してしまいます。解説を読んで満足してしまったり、練習問題でつまずいて放置したりするケースが典型的です。
そのため、物理のエッセンスを最後までやり切り、物理の成績を効率的に向上させるためには、皆さんの学習に合わせた補助的な問題集、参考書を併用することがおすすめです。
- 基礎問題精講:物理のエッセンスが難しいと感じる場合に有効。よりやさしい問題でイメージを固め、学ぶべきことを見つける役割。
- 良問の風:物理のエッセンスで基礎を固めた後に進めたい1冊。典型的な問題で入試で出題される問題のイメージを掴むための役割。
- 名問の森:難関大志望者には必須。応用力を養うための定番で、物理のエッセンスで身につけた思考と解法の型を応用する練習になる。
各参考書のアマゾンリンクはこちら↓
たとえば、エッセンスの解説がどうしてもピンとこない箇所があれば、一度立ち止まって「基礎問題精講」などのやさしめの問題集に戻り、その中で考え方を具体的にイメージしてから再びエッセンスに取り組むと理解が進みます。逆に、先に「良問の風」などに目を通すことで、実際の入試問題のパターンをイメージすることができます。この状態で物理のエッセンスに戻ると「この解法はこういう問題で使うのか」と納得しやすく、定着が確実なものになっていきます。
結局のところ、物理の成績を伸ばすカギは「問題が解けるかどうか」ではなく、解法や概念を正しく整理し、体系化して理解を深められるかにかかっています。その意識を持って取り組むことで、物理のエッセンスは単なる「教科書」ではなく「物理を学ぶ土台」として皆さんの学習を促進するものへと機能します。
真似すれば物理ができるようになる!物理のエッセンスの勉強法
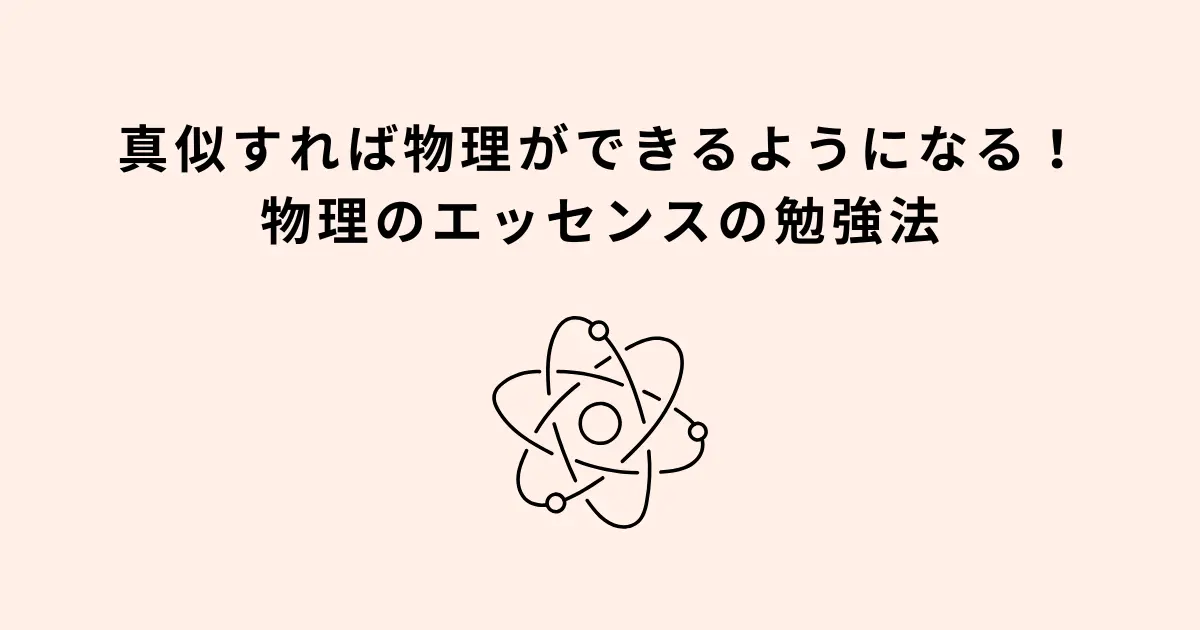
これまでお伝えしてきたように、物理のエッセンスを用いた学習のポイントは、一冊で完結させることにこだわるよりも、他の参考書や問題集を必要に応じて同時並行で進めながら、知識を体系化していくことです。大切なのは「この問題が解けたかどうか」ではなく、「なぜその解法になるのか」「他の分野とどうつながるのか」を意識しながら整理できているかです。
では正しく物理のエッセンスや、周辺の参考書・問題集を活用する方法について、紹介していきます。
効果的な勉強計画(1周目〜3周目)
まず重要なのは、次の2つのポイントを覚悟することです。
- 物理のエッセンスは、1周するだけで完璧にすることはできない。2周3周することを覚悟しておく。
- 物理のエッセンスは、単独で完結させることは難しい。ほかの参考書や問題集を併用して理解を深めていく。
この2つのポイントを注意した上で、その上で以下に示す勉強スケジュールと注意点を参考にし、計画を立ててみてください。
① 物理のエッセンスの1範囲を、順番通りに進めて現状を把握する。(1周目)
→ まずは説明をしっかり読み、適宜ノートに要点を書き出しましょう。ここで意識すべきは次の3つです。
・説明を読み飛ばさないこと
・「なぜその式になるのか」「どんな考え方でその解法に至っているのか」まで気にすること。
・自分で図を描いて、現象をイメージすること。
この3つを必ず守って、分からないことを明確にする目的として1周目を進めてみましょう。
他の参考書や問題集を使うタイミングは、上記で示した3つのポイントをやった上で理解が追いつかない場合です。
物理のエッセンスでは、どうしても「問題が解ける」に焦点が当てられているため、図が乏しい分野や計算を理解するのが難しい問題もあります。その際には「宇宙一わかりやすい高校物理」や「漆原の面白いほどわかるシリーズ」を活用し参照しましょう。
各参考書のアマゾンリンクはこちら↓
② 物理のエッセンスで、同じ範囲を再度読んで解き直す。(2周目)
→ 1周目で現象をイメージし、公式の導出過程を学んだら、それを自分の力で再現できるか確認しましょう。単に答えが合うかどうかではなく、「なぜその式変形になるのか」「どのような考え方で導いているのか」を説明できる状態を目指してください。
説明ができないならば、「理解が浅い」ということです。その際には、他の問題集を併用して別の角度からアプローチするのも効果的です。「良問の風」などの入試問題に近い問題に触れた上でエッセンスに戻ると、解法の意図がより鮮明に理解できるようになります。
解答が合ったかどうかではなく、図を交えて「なぜその式になるのか」「どの前提からその解法が導かれるのか」を自分の言葉で説明できるまで、同じ問題を間隔をあけて繰り返しましょう。
③ 物理のエッセンスの問題を解き進める。(3周目)
→ 3周目ではスラスラと迷わず解けるかを確認しましょう。途中で立ち止まり時間がかかってしまう場合には、まだ定着しきれていない証拠です。その場合は印をつけて後日もう一度やり直し、完全に説明できる状態に仕上げましょう。
そして、その後は続く範囲に進みながら、「良問の風」など標準的な入試問題集を同時並行で解き進めることが理想です。物理のエッセンスで学んだ解法を実戦問題に適用することで、知識が点から線へとつながり、体系化が一気に進みます。
やり方の注意点
ここからは、実際に「物理のエッセンス」を使って学習するうえでの具体的な注意点です。これらは単に本書に限った話ではなく、物理を使う受験生全員が守るべき正しい物理の勉強法です。
①単元ごとに区切って「理解と演習」を反復しよう
物理は積み上げ科目です。力学が分からなければ波動や電磁気は絶対に伸びません。1冊を最初から最後まで読み流すのではなく、1単元ごとに「理解→演習→理解→演習→・・・」のサイクルを作ることが重要です。中途半端に次へ進まず、理解と演習を繰り返すことで、入試本番でも安定して得点できる力が身につきます。
②必ず図を描きながら理解しよう
物理の学習で最も重要なことは、現象を理解し直感的な立式ができるかどうかです。その際に「自分の手で描いた図」は大きなヒントとなります。力学なら力の図示や運動のイメージ、波動なら波の様子や図形の性質、電磁気なら磁場や電流の方向を描き出すことを必ず実践しましょう。公式を丸暗記するのではなく、図を通して意味をイメージできるかどうかが合否を分けます。
③赤字だけに注目しない!公式の暗記はNG
物理のエッセンスを進めている学生さんは要注意です。「物理のエッセンスの赤字部分だけを覚えればいい」と考えるのはかなり危険です。入試では、公式の形そのものより、「なぜその公式になるのか」が問われます。暗記に偏ると、少しひねられただけで解けなくなります。また公式を覚えていないことに、急に不安になりその後の小問が解けなくなる事態に陥ります。必ず公式の導出過程に立ち戻り、根拠を押さえたうえで演習に臨みましょう。
④問題に左右されず解き方を安定させよう
「この問題は解けたけど、別の問題では解けない」という状態は、まだ解き方が定着していない証拠です。この状態では、到底受験に出題される初見問題には対応できません。大切なのは、問題ごとの小手先のテクニックではなく、どんな形式でも同じ流れで解法を再現できる「安定感」を目指すことです。そのためには、同じ分野の問題を繰り返し解き、説明できるまで反復することが欠かせません。
物理のエッセンスの次にやる参考書
物理のエッセンスを終えたら、次に取り組むべきことは2点です。
- 弱点の探索=知識が曖昧になっている箇所がないか?
- 演習力の向上=初見の入試問題を自分で解き進められるか?
この2点を進めるための参考書について、以下で紹介していきます。ここで重要なのは、「諦めずに手を動かして考え抜くこと」と「解説から学び知識を整理すること」です。そして、解いている中で理解が浅いと感じたら、そのまま進まずに必ず物理のエッセンスに戻って確認すること。この往復が、知識を体系化し本番で安定した得点につながります。
良問の風
エッセンスで学んだ解法を整理し、標準的な入試問題で使えるかを確認するための1冊です。すべての問題をスラスラ解けるか、目にした瞬間に解法が思いつくかを基準に学習を進めましょう。入試の典型問題が一通り網羅されているので、良問の風を仕上げればMARCHや国公立大学で必要な知識を整理することができるはずです。
共通テスト・センター試験対策問題集
共通テストやセンター試験形式の問題集は、時間配分の感覚を養うことと、暗記が重要になる単元の確認に最適です。特に波動・熱力学・原子分野では暗記事項の正確さが得点に直結します。理解や記憶が曖昧な分野を発見し、物理のエッセンスで復習するというサイクルを繰り返しましょう。
名門の森
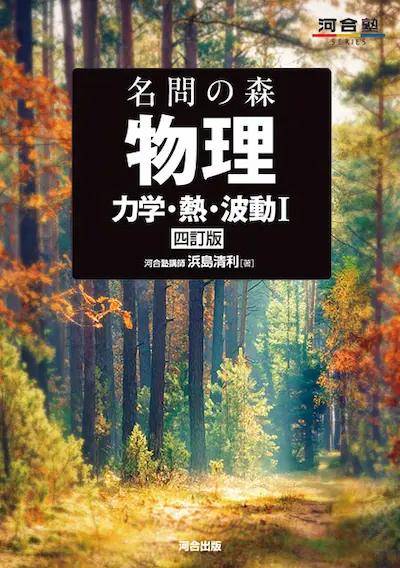
国公立大学の2次試験や難関私大で高得点を目指す受験生は、名問の森がおすすめです。入試問題の中でも応用的でひねられた良問が多く、思考力を問う出題に慣れることができます。ここで問われるのは「解けるかどうか」ではなく、「解法を自分の中で体系化し、どんな切り口の問題にも対応できるか」です。過去問で解けなかった問題を名問の森で類題として探し、演習を積むことで、弱点を確実に潰せます。過去問演習で出てきた「自分の弱点」を、名問の森で補強するイメージで取り組むと効果的です。
過去問
最終的に物理の得点力を仕上げるのは、やはり過去問演習です。志望校の出題傾向を把握し、自分の答案を本番形式で採点することで、合格点まであと何が足りないのかが見えてきます。そして解けなかった問題は、しっかりと解説を読み込みましょう。
併せて「名問の森」や類題集に戻って演習を重ねましょう。こうすることで「過去問でしか見ない一発勝負の問題」ではなく、「同じタイプの問題を確実に解ける力」に変えていくことができます。
まとめ
「物理のエッセンス」は大学受験物理の定番参考書であり、正しく使えば基礎の定着から共通テスト8割、さらに国公立中堅大レベルまで到達できる力を養うことができます。ただし、内容が優れている一方で注意が必要です!
この記事で紹介したような注意点を参照し、物理を得点源に変えるための最強の土台を作っていきましょう。
理系専門塾SoRaでは、物理をはじめとする理系科目の学習を「どの参考書を、どの順番で、どのように使うか」まで徹底的にサポートしています。もしあなたが「物理のエッセンスを使っているのに伸びない」「参考書の進め方が分からない」と感じているなら、ぜひ一度ご相談ください。正しい方法で取り組めば、物理は必ず得点源になります。
【一緒によく読まれている記事】
- 偏差値を爆上げ!する青チャートの勉強法やいつまでにやるべきかを解説
- 偏差値を爆上げ!黄チャートの効果的な使い方、何日で終わるかと注意点を徹底解説
- 【2025年版】北大の理系数学を攻略!青チャートの次にやるべき問題集は?
【LINE友だち追加特典】
—❶ 数学やるべき参考書MAP
現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、
今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。
・ 学力段階ごとにおすすめの参考書
・ どんなタイプの人に向いているか
・ 使うときに気をつけるポイント
などを具体的に解説しています。
—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム
公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。
このコラムでは、
実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、
高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。
・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方
・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法
・ 部活動と勉強を両立する考え方
・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法
など、
少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。
ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。