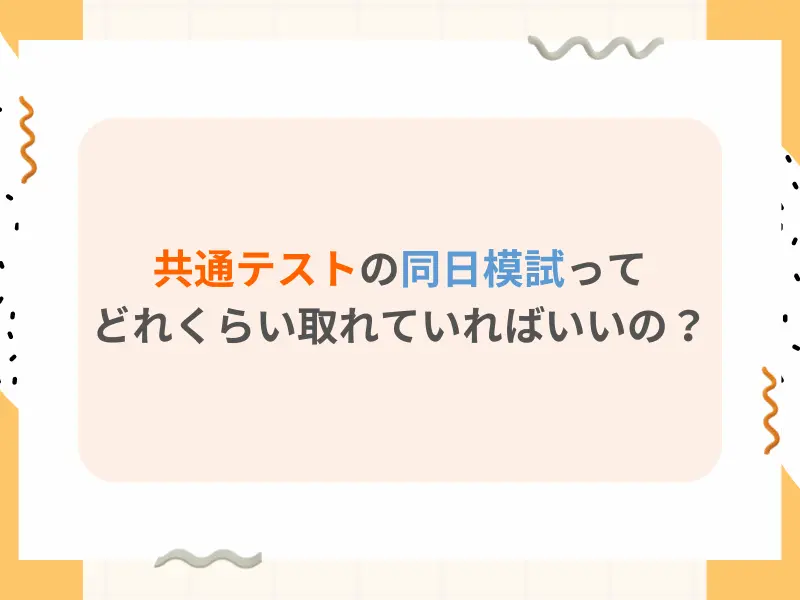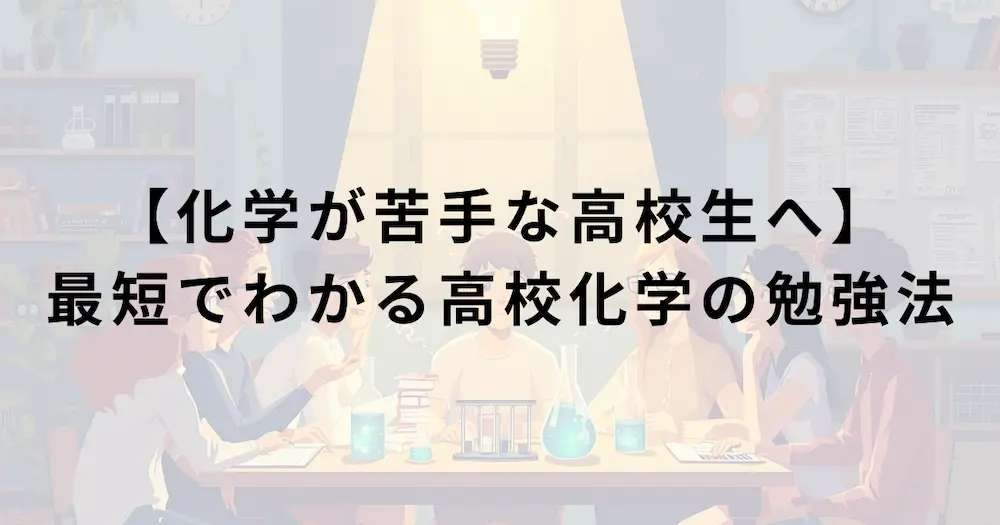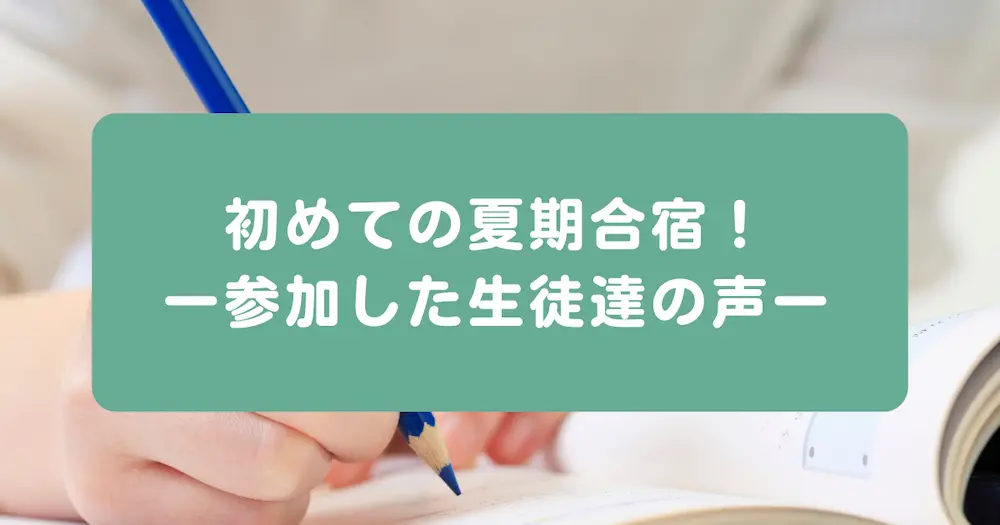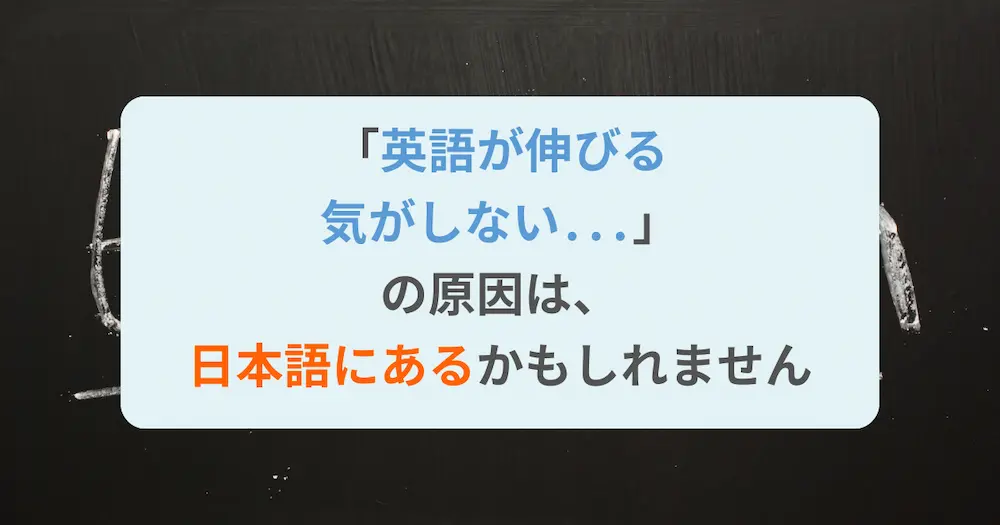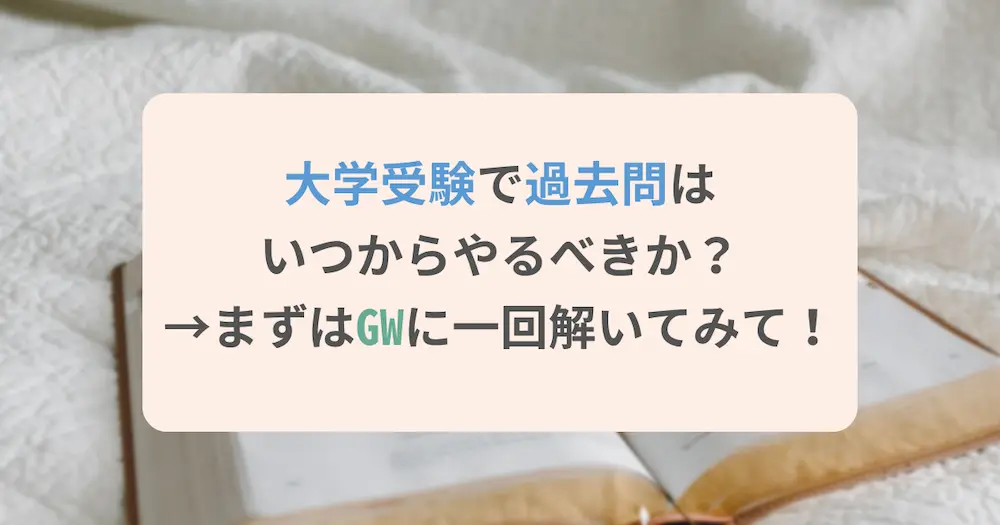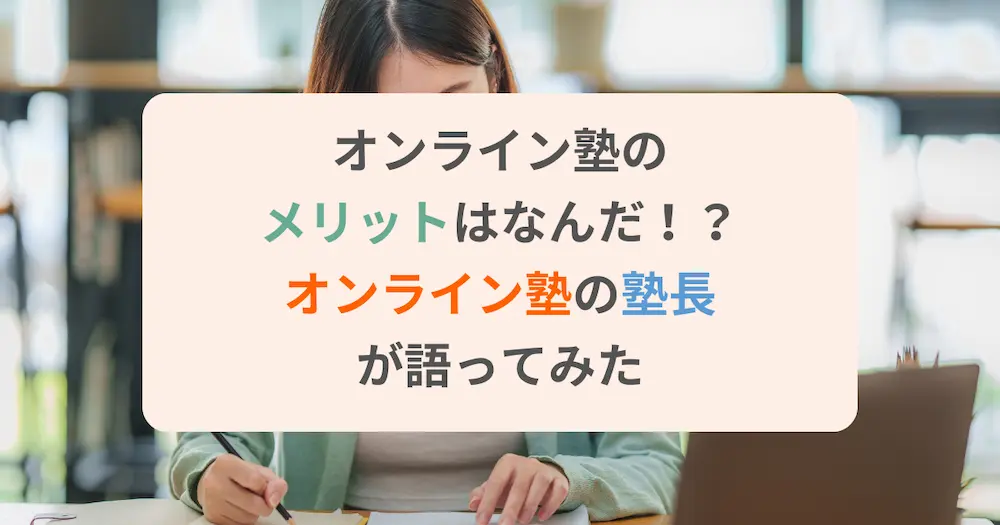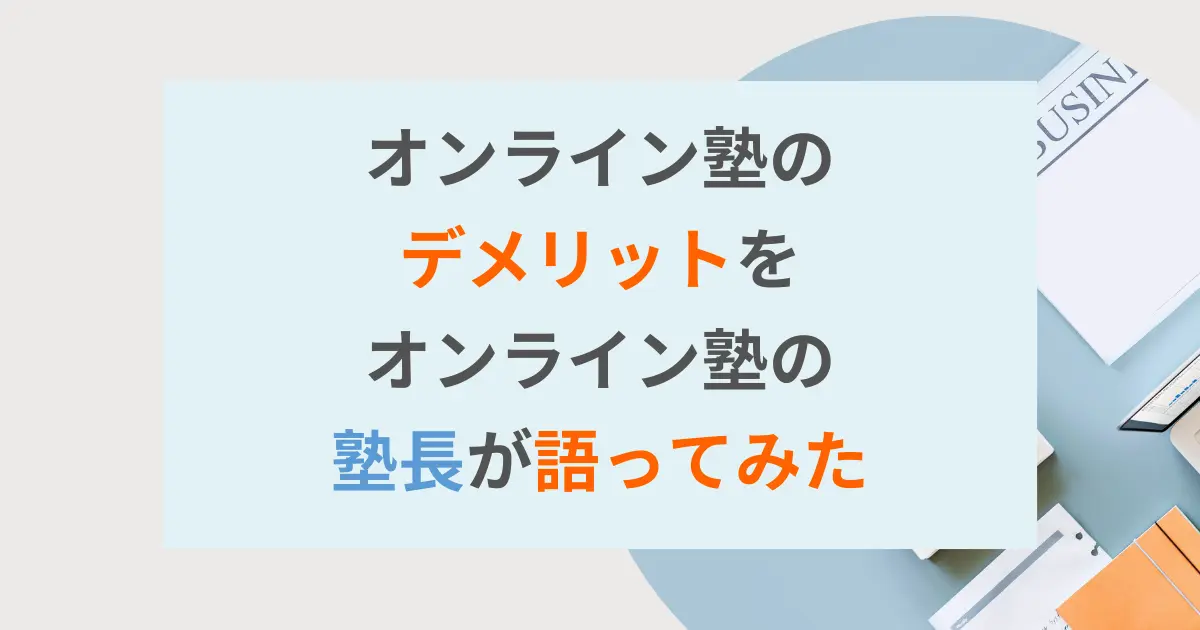1ヶ月で模試のベクトルで満点を取った生徒がやっていたこと

この前の4月末に行われた全統共通テスト模試でベクトルで満点を取ったと報告してくれた子がいました。
その子は浪人生で、現役の時はベクトルを使わない受験方式だったため、学校で習って以来4月からベクトルを再度勉強し始めた子です。
つまり、1ヶ月ちょっとの間ベクトルを勉強して、共通テスト模試で満点をとるレベルまで到達しました!(これはベクトルを勉強したことがある人なら、いかにすごいことかわかると思います)
当塾の指導でここまでになったという自慢ではなく、この子自身の能力と努力によるところが当然大きいです。
しかし、なぜそこまで短期間で伸ばすことができたのか、その要因は何なのかをその子とのやりとりの中で、具体的に見えてきたので今回言語化してみたいと思います。
ベクトルを1ヶ月で習得できた秘訣は主に2つあります。
問題集の作成者の意図を汲み取る
1つは、問題集の作成者の意図を汲み取ろうとしながら勉強しているということです。その子は、その問題集に載っている問題や解説にどういった意図があり、そこから何を伝えようとしているのかを必死に読み取っていました。
ある日の質問で、「私の解き方と解説のやり方が違っていて、解説ではなぜこのように書かれているのですか?」というのを聞かれました。
普通、質問と言ったら、「この問題がわからないので教えてください」という趣旨の質問が多いです。もちろん、これらの質問が悪いわけではありません。
しかし、その子は、答えの正誤だけでなく、解説で書かれていることの意図まで汲み取ろうとしていたわけです。
これは結構高度なことだと思います。ほとんどの受験生はそこまで意識できていないし、意識しようと思っても習慣化するまでは難しいです。
でも、問題を解けるのを良しとするだけでなく、その問題や解説の意図まで掴もうという姿勢でいたら、初見の問題でも見え方は変わってきます。
入試では受験生の能力を図るために問題を出しているわけなので、何の力を問われているのか、メタ的な視点で問題を見れるようになり、問題の難しさやポイントがわかるようになります。
問題集のやり方に素直に従ってみる
2つ目は、問題集のやり方に素直に従ってみるということです。1つ目と比べると、だいぶハードルの下がった内容であるものの、逆にハードルが低すぎるが故に意外と実践できている人は少ないんじゃないかなと思います。
この子は当塾で使用している教材「数学リニア(高校数学を最短最速で終わらせられるように設計された塾の教材)」を使用しています。
詳細はこちらから↓
数学リニアの何がすごいのか、理系専門塾塾長が語ってみた
その教材では、事細かに問題をどう解いてほしいのか指示してあります。たとえば、「ベクトルの矢印の図をかけ」「問題文もそのまま書き写せ」「理由と具体例をあげよ」と言った指示が一部の問題にあります。また、どの問題が何分以内にできたら次に行っていいのかという基準も明確に定まっています。
要は、生徒からすると面倒な指示がたくさんあるのです笑
他の教材でも、面倒な指示がたいてい最初の方のページにあり、どのように使っていくことを想定しているのか、あるいはどのように使って欲しいのかが書いてあります。
これらは、問題集を作っている人が面倒なことを受験生に押し付けようと思ってそういった指示を書いているのではなく、本当に必要だと思っているから書いているのです。
結局勉強に限らず、面倒なことの向こう側でしか見えないことがあります。
それを面倒だからやらない、ちょっとサボっちゃおうという意識でいると、結局成績が充分には伸びないのです。
たしかに、その指示の必要性を完璧に理解するのは難しいです。けども、まずは素直に全力でやってみてください。そこで自分ができていない箇所や思っていたより理解できていなかった箇所が見つかれば万々歳です。逆にそういった箇所がなければ、時間をかけるべきところを選定して、もっと先に進めるだとか、解説の読み込みに時間をかけるだとか、別のところに時間をかけていけばよいのです。
いきなりオリジナのやり方でやろうとせずに、まずは素直に取り組んでみましょう。
とは言っても、全員が最初からこれら2つのことをできるわけではないので、当塾ではみんながその境地に達せられるように指導の日々が続いていきます。
まとめ
ベクトルを1ヶ月で習得できた秘訣
- 問題集の作成者の意図を汲み取ろうとしながら勉強している
- 問題集のやり方に素直に従ってみる
【関連記事】
・高1生、定期テストの数学が18点UP!!
・数学リニアを使って4ヶ月で模試の偏差値58.6→ 65.2へ
・数学リニアの何がすごいのか、理系専門塾塾長が語ってみた
【LINE友だち追加特典】
—❶ 数学やるべき参考書MAP
現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、
今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。
・ 学力段階ごとにおすすめの参考書
・ どんなタイプの人に向いているか
・ 使うときに気をつけるポイント
などを具体的に解説しています。
—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム
公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。
このコラムでは、
実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、
高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。
・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方
・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法
・ 部活動と勉強を両立する考え方
・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法
など、
少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。
ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。